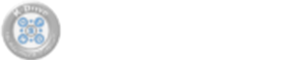概要
鈴鹿高専独自の施策である産学官協働研究室をさらに進化させ、全国高専の教職員、学生、企業技術者が参画可能な高専ネットワーク援用産学官協働研究チーム「K-Team」を開設し、先端マテリアルの社会実装に取り組む。K-CIRCUIT はK-Team の開設に必要な規則や運営ノウハウをパッケージ化し、K-Drive 内へのK-Team 設置制度の構築を支援する。また、社会ニーズに適格に応じることができる人財と設備とをマッチングしたK-Team を構築してK-Drive内に展開する。K-Team の構成についてはデータベースを活用し、取り組む研究テーマに最適かつ多様な人財を参加させることで、オープンイノベーションを誘発して協働研究成果の社会実装を加速させる。またK-Team はデータバンクにアクセスして必要とする人財や設備を抽出し、研究の進捗に応じてオンタイムな支援を受けられるシステムを構築する。すなわち、一企業対一教員、一企業対一高専という古い産学連携態勢を脱却し、企業対K-Driveという新しい産学官連携スタイルによって先端マテリアルテクノロジーの社会実装を実現する。
ア)複合材料研究室(ミズノテクニクス)
ミズノテクニクス株式会社の研究者2名と本校の機械工学科、材料工学科の教員4名により構成された研究室で、スポーツ用具(例:ゴルフクラブのシャフト)および産業用材料(例:水素自動車の水素タンク)に用いる樹脂にCNT(Carbon Nanotube)を分散させた高強度CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics)の研究に取り組んでいる。機械工学科は疲労強度特性にCNTが与える影響について評価しており,材料工学科は、CNTの分散性の観察と基礎物性評価を担当している。
イ)AIフロー合成機開発室(東京化成工業)
東京化成工業株式会社の研究員3 名と本校の生物応用化学科、電子情報工学科、機械工学科の教員5 名により構成された研究室で、「フロー合成機と分析装置を連結し、コンピュータ制御により、多品種の化学品の合成反応条件を比較的短時間で自動的に最適化する小型汎用装置の開発」を目的とした研究に取り組んでいる。生物応用化学科、機械工学科がフロー合成機と分析装置の連結部分、電子情報工学科がコンピュータ制御の部分を担当している。
ウ)AVEX未来創造研究室(エイベックス株式会社)
切削研削加工技術の追求と自動化やデジタル技術導入によるスマートファクトリー実現の研究開発を目的とし、新たな市場創造が実現できるよう、主要技術である精密切削研削の更なる加工条件追及により、高精度や難削材の省人加工を実現させる。また、自社内で容易に獲得や向上が困難なデジタル技術を用いた自動化や効率化を支える新たな導入に向けた研究・開発等を推進する。
エ)MonotaRO 品質評価研究室(株式会社MonotaRO)
モノタロウ プライベートブランド商品の性能・品質の評価解析に関する教育・研究である。それらの教育・研究に対して、株式会社MonotaROの研究員5 名と、本校の生物応用化学科の教員3名と学生が密に連携して取り組んでいる。
オ)ハイドロネクスト水素協働研究室(株式会社ハイドロネクスト)
水素社会の実現に向けて水素精製技術の確立が求められていることから、教員と学生及び企業の連携による次世代水素透過金属膜の研究開発と実装製品の検証を行い、効率的な超高純度水素精製技術の開発、水素透過膜の耐久性評価法の確立、コンビナート副生ガスに対応可能な技術の選定などを目的として、先端マテリアルテクノロジーの社会実装を実現する。